×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
こちらが開催されます。

IVVオリンピアード。
↑
クリックすると概要がわかります。
といっても、私の住む山梨県の国中地方では、「なにがはじまるの?」って感じで、今2つ3つ、盛り上がりに欠けているような気もしますが・・・。
が、「勝ち負けを競うことが目的の大会ではありません。スポーツを通じて美しい自然とふれあい、国を越えた人々との親睦・交流をも楽しめる、世界中の誰もが自由に参加できる国際大会です。」と、ホームページにも記載があるとおりだと私も思っていますので、参加後の報告は改めてアップさせていただきます。。
IVVオリンピアード。
↑
クリックすると概要がわかります。
といっても、私の住む山梨県の国中地方では、「なにがはじまるの?」って感じで、今2つ3つ、盛り上がりに欠けているような気もしますが・・・。
が、「勝ち負けを競うことが目的の大会ではありません。スポーツを通じて美しい自然とふれあい、国を越えた人々との親睦・交流をも楽しめる、世界中の誰もが自由に参加できる国際大会です。」と、ホームページにも記載があるとおりだと私も思っていますので、参加後の報告は改めてアップさせていただきます。。
PR
こんにちは。
うちの事務所に営業に来られる業者さんが、毎月、社団法人・倫理研究所発行の「職場の教養」という小冊子を持ってきてくれます。
この冊子は、毎日毎日の教訓や戒めが載っていまして、毎朝、日報を付けると同時に目を通すと1日が充実したような気分になるものです。
実は、昨日のブログに書いていた、「小淵沢」の駅名を「小渕沢」と打ち込んだ時に、誤字だったことに暫らく気付きませんでした。
先日も、この「職場の教養」で、“35歳以上の「大人の漢字活用能力」の調査では、85%が「自分の漢字の読み書き能力が低下した」と感じ、理由は「文字を書く機会が減った」からである。なので、辞書を引きましょうね。という件を読んだばかりなのに、しっかり自身がポカをしていたんですね。おはずかしい。。
笑える変換ミスなら、このようにブログにも書く事が出来ますが、書類等にこんな間違いを記載してしまったらと思うと・・・・・。
やはり、辞書を引く習慣をつけるようにしていないといけませんね。
(でも、小さい文字がだんだん読みずらくなってきているんですよね~。)
うちの事務所に営業に来られる業者さんが、毎月、社団法人・倫理研究所発行の「職場の教養」という小冊子を持ってきてくれます。
この冊子は、毎日毎日の教訓や戒めが載っていまして、毎朝、日報を付けると同時に目を通すと1日が充実したような気分になるものです。
実は、昨日のブログに書いていた、「小淵沢」の駅名を「小渕沢」と打ち込んだ時に、誤字だったことに暫らく気付きませんでした。
先日も、この「職場の教養」で、“35歳以上の「大人の漢字活用能力」の調査では、85%が「自分の漢字の読み書き能力が低下した」と感じ、理由は「文字を書く機会が減った」からである。なので、辞書を引きましょうね。という件を読んだばかりなのに、しっかり自身がポカをしていたんですね。おはずかしい。。
笑える変換ミスなら、このようにブログにも書く事が出来ますが、書類等にこんな間違いを記載してしまったらと思うと・・・・・。
やはり、辞書を引く習慣をつけるようにしていないといけませんね。
(でも、小さい文字がだんだん読みずらくなってきているんですよね~。)
こんにちは。
普段列車に乗る時といえば、甲府~新宿・東京間の「かいじ」又は「あずさ」でしたが、昨日小淵沢からの帰りに初めてこちらの列車に乗る機会がありました。

こちら、週末の土日に上りと下り1本づつ運転されている、「ホリデー快速ビューやまなし号」という列車です。
こちら、一番の魅力は、「2階立ての列車」であることなんですね。
それと、「快速」なので、小淵沢~甲府間の停車駅は、わずか韮崎駅のみですし、
自由席であれば普通乗車券のみで乗れるというのもうれしい限りです。(ほんと、まったくこんな列車があることなぞ、今の今まで知りませんでした。)
当然2階席に上がりましたが、ちょっと視界が良いだけでも、ものすごーく得した気分。

小淵沢~甲府間の乗車でしたから、座席もガラガラでしたしね。
一度は、「新宿~小淵沢間」まで、駅弁とお茶をもって、ゆっった~り乗車してみたいものです。
普段列車に乗る時といえば、甲府~新宿・東京間の「かいじ」又は「あずさ」でしたが、昨日小淵沢からの帰りに初めてこちらの列車に乗る機会がありました。
こちら、週末の土日に上りと下り1本づつ運転されている、「ホリデー快速ビューやまなし号」という列車です。
こちら、一番の魅力は、「2階立ての列車」であることなんですね。
それと、「快速」なので、小淵沢~甲府間の停車駅は、わずか韮崎駅のみですし、
自由席であれば普通乗車券のみで乗れるというのもうれしい限りです。(ほんと、まったくこんな列車があることなぞ、今の今まで知りませんでした。)
当然2階席に上がりましたが、ちょっと視界が良いだけでも、ものすごーく得した気分。
小淵沢~甲府間の乗車でしたから、座席もガラガラでしたしね。
一度は、「新宿~小淵沢間」まで、駅弁とお茶をもって、ゆっった~り乗車してみたいものです。
こちらの駅弁を食べる機会がありました。

ご存知ですか?
もう25年程度も前にテレ朝の番組企画で出来上がった、小淵沢は丸政さんのお弁当です。
大学生の頃、リアルタイムでこの番組を友人たちと見ていたときに、私の帰省時のお土産は、小淵沢駅にいってこのお弁当を持って帰ってくることが義務付けされてしまったのでした。
当時いくらだったかも覚えていませんが、このお弁当1つが、ほかの駅弁2つ分くらいの値段だったようで、友人3~4人分と私の分を含めて大そうな金額を払ったような気がしています。(というより、学生だったために異常に高く感じていたのかもしれません。)
当時のエピソードがパッケージに書かれていました。
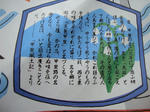
懐かしいですよね。
久しぶりに頂きましたが、当時のままの安西水丸のこのイラストは、今でも新鮮に感じます。
また、味も当時と変わらずおいしいです。(といっても既にお弁当の中身は記憶にありませんでしたが。)
小淵沢駅で購入するからこそ価値のある駅弁、「元気甲斐」でした。
ご存知ですか?
もう25年程度も前にテレ朝の番組企画で出来上がった、小淵沢は丸政さんのお弁当です。
大学生の頃、リアルタイムでこの番組を友人たちと見ていたときに、私の帰省時のお土産は、小淵沢駅にいってこのお弁当を持って帰ってくることが義務付けされてしまったのでした。
当時いくらだったかも覚えていませんが、このお弁当1つが、ほかの駅弁2つ分くらいの値段だったようで、友人3~4人分と私の分を含めて大そうな金額を払ったような気がしています。(というより、学生だったために異常に高く感じていたのかもしれません。)
当時のエピソードがパッケージに書かれていました。
懐かしいですよね。
久しぶりに頂きましたが、当時のままの安西水丸のこのイラストは、今でも新鮮に感じます。
また、味も当時と変わらずおいしいです。(といっても既にお弁当の中身は記憶にありませんでしたが。)
小淵沢駅で購入するからこそ価値のある駅弁、「元気甲斐」でした。
こんにちは。
今週は、最近読んだ本やお気に入りの本を紹介しながらの1週間でした。
で、週末の今日は、本に纏わる小物をご紹介したいと思います。

左は昨日のブログでご紹介した「コーヒーハンター」です。
その上にコマゴマしたものが乗っていますが、こちらは本を読む時に愛用している小物の“しおり”です。
右上のちょっと大きめのものは「マネークリップ」です。
これは、新書に挟まっているチラシや、本を読んでいて気になったことをメモした時など、表紙の裏側に落とさず挟み込んでおくときなどに重宝しています。数ページ一気にマーキングする時などにも適しています。
左側の二つは、読みかけ中のページのマーキングに使っています。
スマイルマークのクリップと、矢印型のブックダーツ。
スマイルマークは、シリアスな読み物や専門書などの堅い物のときに、少しでもなごむようにあえて使うようにしていますし、ブックダーツは、読みかけの行まで指定してマーキングできるので、「さっき何処まで読んだんだっけ・・・」って解らなくなって、何ページか遡ってまで読み返さなくて済みます。
ただし、持ち歩く時にずれないように注意して手に取る必要はありますが。
でも、一番多くしおりとして使っているのは、出張時に紀伊国屋書店で掘り出し物を見つけてくることが多いので、意外とJR中央線の特急券を使っていたりします。
ということで、今日は「本」の番外編として「しおり」をいくつかご紹介いたしました。
今週は、最近読んだ本やお気に入りの本を紹介しながらの1週間でした。
で、週末の今日は、本に纏わる小物をご紹介したいと思います。
左は昨日のブログでご紹介した「コーヒーハンター」です。
その上にコマゴマしたものが乗っていますが、こちらは本を読む時に愛用している小物の“しおり”です。
右上のちょっと大きめのものは「マネークリップ」です。
これは、新書に挟まっているチラシや、本を読んでいて気になったことをメモした時など、表紙の裏側に落とさず挟み込んでおくときなどに重宝しています。数ページ一気にマーキングする時などにも適しています。
左側の二つは、読みかけ中のページのマーキングに使っています。
スマイルマークのクリップと、矢印型のブックダーツ。
スマイルマークは、シリアスな読み物や専門書などの堅い物のときに、少しでもなごむようにあえて使うようにしていますし、ブックダーツは、読みかけの行まで指定してマーキングできるので、「さっき何処まで読んだんだっけ・・・」って解らなくなって、何ページか遡ってまで読み返さなくて済みます。
ただし、持ち歩く時にずれないように注意して手に取る必要はありますが。
でも、一番多くしおりとして使っているのは、出張時に紀伊国屋書店で掘り出し物を見つけてくることが多いので、意外とJR中央線の特急券を使っていたりします。
ということで、今日は「本」の番外編として「しおり」をいくつかご紹介いたしました。
こんにちは。
今週1週間の「本」の話の締めは、やはりこちらでしょ。
「コーヒーハンター」・・・川島良彰 著 です。
私がこの本のことを知ったのは、1月11日の日経新聞1面下帯の「春秋」のコメントがあまりにもいかしていて、氏のことをもっと知りたくなって手にしたのがこの本だったのでした。
その、日経新聞の魅惑的な文章とは、こちら。
シャンパンボトルの封を切りコルク栓をゆっくりと抜く。ポンという音と共にあふれたのは泡でも酒でもなく、焙煎直後のコーヒー豆の豊かな香り。大手コーヒー会社役員を五十歳過ぎで辞めた川島良彰さんが、一風変わったコーヒー豆の会員制販売を始めた。・・・・・(と文章はまだまだ続きます。)
まず、私が手にした本を読んでみると、子供の頃からコーヒーの生豆の麻袋の上を格好な隠れ家としていた少年が、高校卒業待たずしエルサルバドルへ旅たつところからこの本はスタートします。
あまり日本にも情報の流れていない地域ということもあってか、余計に期待感も高まってきますし、とにかく痛快で、読むほどにぐいぐい本の中に引き込まれていく、素敵な1冊です。
1杯のコーヒーの前にこちらの本もどうぞ。
今週1週間の「本」の話の締めは、やはりこちらでしょ。
「コーヒーハンター」・・・川島良彰 著 です。
私がこの本のことを知ったのは、1月11日の日経新聞1面下帯の「春秋」のコメントがあまりにもいかしていて、氏のことをもっと知りたくなって手にしたのがこの本だったのでした。
その、日経新聞の魅惑的な文章とは、こちら。
シャンパンボトルの封を切りコルク栓をゆっくりと抜く。ポンという音と共にあふれたのは泡でも酒でもなく、焙煎直後のコーヒー豆の豊かな香り。大手コーヒー会社役員を五十歳過ぎで辞めた川島良彰さんが、一風変わったコーヒー豆の会員制販売を始めた。・・・・・(と文章はまだまだ続きます。)
まず、私が手にした本を読んでみると、子供の頃からコーヒーの生豆の麻袋の上を格好な隠れ家としていた少年が、高校卒業待たずしエルサルバドルへ旅たつところからこの本はスタートします。
あまり日本にも情報の流れていない地域ということもあってか、余計に期待感も高まってきますし、とにかく痛快で、読むほどにぐいぐい本の中に引き込まれていく、素敵な1冊です。
1杯のコーヒーの前にこちらの本もどうぞ。
こんにちは。
今日からお仕事という方も多いんでしょうか?それとも、今日・明日も続けてお休みをとっていらっしゃる方もいるんでしょうか?
今週はカテゴリーが「本」で進めていますので、明日まで、「こんな面白い本がありますよ~。」の話を続けたいと思います。
子供の頃に、「最初は4本足。次は2本足。最後には3本足となるものは何だ?」ってなぞなぞをしたことは、皆さんも記憶にありますか?
この答えが出来ない人はスフィンクスに食い殺されたという、ギリシャ神話からのお話なのですが・・・。
(大丈夫、答えはご存知ですよね。)
私も「すまい」もこの答えのように、成長するものなのだと以前からブログでも書いてきています。
今日お話しする本は、このなぞなぞの「3本足」になった時の為に考えた方がよい「すまい」に関する本です。
そのタイトルも ズバリ、「減築のすすめ」講談社発刊です。
読まずしても、大体中身は想像できますよね。
それでいて、期待を裏切りません、この本は。
ところどころ。「あるよねー、こんな話。うんうん。。」って首を縦に振りながら読み終えたくらいですから。
ただし、やはり主眼は設計事務所主催者の眼で見て書かれた本になりますから、同様な工務店主催者側から書かれた本に比べ、微妙に“上から目線”もあります。
(それが逆に工務店側の著者作品に比べ、紳士的な表現になっているので好感が持てるんですけどね。)
しかし、新築時のときからこの考え方を踏んだ建物を計画できていれば、生活しやすくなるでしょうね。
今日からお仕事という方も多いんでしょうか?それとも、今日・明日も続けてお休みをとっていらっしゃる方もいるんでしょうか?
今週はカテゴリーが「本」で進めていますので、明日まで、「こんな面白い本がありますよ~。」の話を続けたいと思います。
子供の頃に、「最初は4本足。次は2本足。最後には3本足となるものは何だ?」ってなぞなぞをしたことは、皆さんも記憶にありますか?
この答えが出来ない人はスフィンクスに食い殺されたという、ギリシャ神話からのお話なのですが・・・。
(大丈夫、答えはご存知ですよね。)
私も「すまい」もこの答えのように、成長するものなのだと以前からブログでも書いてきています。
今日お話しする本は、このなぞなぞの「3本足」になった時の為に考えた方がよい「すまい」に関する本です。
そのタイトルも ズバリ、「減築のすすめ」講談社発刊です。
読まずしても、大体中身は想像できますよね。
それでいて、期待を裏切りません、この本は。
ところどころ。「あるよねー、こんな話。うんうん。。」って首を縦に振りながら読み終えたくらいですから。
ただし、やはり主眼は設計事務所主催者の眼で見て書かれた本になりますから、同様な工務店主催者側から書かれた本に比べ、微妙に“上から目線”もあります。
(それが逆に工務店側の著者作品に比べ、紳士的な表現になっているので好感が持てるんですけどね。)
しかし、新築時のときからこの考え方を踏んだ建物を計画できていれば、生活しやすくなるでしょうね。

