×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
今日は、タイトルから穏やかでない言葉で始まりましたが、
先日とある分譲地で、まるでモデルハウスを競うかのように各種住宅メーカー、地元パワービルダーや工務店が入り乱れた所を見てしまいました。
まーここよりひどい所は、甲府の東側からちょっと視線を上げれば何時でも見れますが。。
私は、このブログを始めて書いた頃から、「崩れた街並みってどうなの?」って話してきましたけど、
(3年前以前に書いた記事は) ↓
http://osumai.blog.shinobi.jp/Entry/24/ と http://osumai.blog.shinobi.jp/Entry/26/
上のブログにも書いてありますけど、これ、小学校の教科書ですよ、教科書。
誰が こうなる前に歯止めをかけるんでしょうか?
土地を販売する人? ハウスメーカー? 設計屋? 工事業者? いや、そこに住む建て主の方なの?
実際のところ、貴方はどのように思いますか?
先日とある分譲地で、まるでモデルハウスを競うかのように各種住宅メーカー、地元パワービルダーや工務店が入り乱れた所を見てしまいました。
まーここよりひどい所は、甲府の東側からちょっと視線を上げれば何時でも見れますが。。
私は、このブログを始めて書いた頃から、「崩れた街並みってどうなの?」って話してきましたけど、
(3年前以前に書いた記事は) ↓
http://osumai.blog.shinobi.jp/Entry/24/ と http://osumai.blog.shinobi.jp/Entry/26/
上のブログにも書いてありますけど、これ、小学校の教科書ですよ、教科書。
誰が こうなる前に歯止めをかけるんでしょうか?
土地を販売する人? ハウスメーカー? 設計屋? 工事業者? いや、そこに住む建て主の方なの?
実際のところ、貴方はどのように思いますか?
PR
今日2回目の書き込みです。
こちらの記事がネットに載っていましたので、忘れないうちにご一読ください。
「大和ハウスさんは、ロボット事業に本気なんですかね」と驚くのは、ある建設会社の幹部だ。
驚くのも無理はない。10月下旬に大手住宅メーカーの大和ハウス工業が相次いで2件のロボット事業を公表したからだ。
1件は、自社開発した住宅床下点検ロボット「moogle(モーグル)」の運用開始であり、もう1件は、電子機器メーカーの知能システムが製造するセラピー用のアザラシ型「パロ」の販売開始だ。
「モーグル」は、LED照明とカメラを備え、無限軌道(いわゆるキャタピラー)で走行する。定期点検やリフォーム前の検査時に、遠隔操作で床下を走らせ、配管状況や基礎部分のひび割れ、シロアリ被害の有無などをパソコン画面でリアルタイムに確認できるのが特徴。作業者が床下に腹ばいになって潜り込む必要がなく、点検作業が軽減できる。
2006年から千葉工業大学と筑波大学との産学共同研究を実施、08年からは三菱電機特機システムと実用化に向けて研究してきた。11年4月1日から関東・中部・近畿地区で50台を配備する。
もう一方の「パロ」は、タテゴトアザラシの赤ちゃんをモデルにしたぬいぐるみのようなロボットだ。その愛らしさに加え、呼びかけたり、なでたりすると反応し、コミュニケーションによって人を“癒す”。1993年から産業技術総合研究所がロボットによる“癒し効果”を目的に開発を開始。04年には知能システムがライセンスを得て、05年から販売しており、今回、11月から大和ハウスが新たな販売先として加わる格好である。
大和ハウスのロボット事業は、08年にベンチャー企業のサイバーダインと総代理店契約を結び、歩行が困難な人でも杖なしで歩けるようにする装着型自立歩行支援ロボット「ロボットスーツHAL」のリース販売を開始したのがきっかけだ。今期40カ所以上の医療・介護施設に約100台のHALを納入しており、今回の2つの案件が加わることで、3種のロボットを取り扱うことになる。
なぜ、住宅メーカーである大和ハウスはロボット事業を行うのだろうか。
それは、将来の少子高齢化を睨んだ多角化戦略の一環だ。今後、ますます人口が減少するなかで新築住宅が先細りになるのは自明の理であるからだ。
厚生労働省によると、05年から25年にかけて、高齢者人口は約1070万人が増加すると予測。比率で言えば、65歳以上の高齢者人口は、現在の 5人に1人の割合から20年前後には約3人に1人にまで増えると予測されている(国立社会保障・人口問題研究所による)。これに対応し、高齢化を支える生活支援ロボットの市場も15年には3700億円、20年には1兆円に達するという試算がある(経済産業省による)。
こうした将来の労働力人口の減少や高齢化に対応し、大和ハウスは、2010年度を最終年度とする3年間の中期経営計画で、ロボット事業をリチウムイオン電池事業や海外(中国)事業などともに、新たな収益源となる次世代事業として強化しているのだ。
ロボット事業推進室の田中一正室長は「当初、2人でスタートした人員も東京と大阪を合わせて35人まで増え、今期で前年度比5倍以上の売上高2億 5000万円を目標としている」と説明する。
床下点検のモーグルは、高齢化が進む建築現場で作業員の負担を軽減するメリットが大きいため、自社グループ内での運用だけでなく、将来的には各地の工務店や建設会社向けの外販も期待できるという。
今回、販売するパロの場合では、日本国内では百貨店経由で販売されてきたこともあり、個人向けの“ペットロボット”という印象が強いが、海外では、米食品医薬品局(FDA)が09年に医療機器として承認しているほか、デンマークでは11年までに1000体の導入を計画し、パロを取り扱う公式な資格が設けられるなど、介護施設向けの介護機器として高く評価されている。
このため、大和ハウスでは、パロをHALとともに、これまで同社が施工してきた約2600カ所の医療・介護施設を中心に販売する考えだ。
ロボット事業は、少子高齢化を懸念するトヨタ自動車やホンダといった自動車メーカーも次世代事業として育成中である。住宅メーカー大手の大和ハウスがどれほど本気で望むのか。冒頭のコメントのように、建設関連業界の注目度も大きい。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 山本猛嗣) 引用させていただきました。
どうですか?
絶対的に必要になると思いませんか?
こちらの記事がネットに載っていましたので、忘れないうちにご一読ください。
床下点検のモーグル、癒し系のパロ…大和ハウスがロボット事業に力を入れる訳
驚くのも無理はない。10月下旬に大手住宅メーカーの大和ハウス工業が相次いで2件のロボット事業を公表したからだ。
1件は、自社開発した住宅床下点検ロボット「moogle(モーグル)」の運用開始であり、もう1件は、電子機器メーカーの知能システムが製造するセラピー用のアザラシ型「パロ」の販売開始だ。
「モーグル」は、LED照明とカメラを備え、無限軌道(いわゆるキャタピラー)で走行する。定期点検やリフォーム前の検査時に、遠隔操作で床下を走らせ、配管状況や基礎部分のひび割れ、シロアリ被害の有無などをパソコン画面でリアルタイムに確認できるのが特徴。作業者が床下に腹ばいになって潜り込む必要がなく、点検作業が軽減できる。
2006年から千葉工業大学と筑波大学との産学共同研究を実施、08年からは三菱電機特機システムと実用化に向けて研究してきた。11年4月1日から関東・中部・近畿地区で50台を配備する。
もう一方の「パロ」は、タテゴトアザラシの赤ちゃんをモデルにしたぬいぐるみのようなロボットだ。その愛らしさに加え、呼びかけたり、なでたりすると反応し、コミュニケーションによって人を“癒す”。1993年から産業技術総合研究所がロボットによる“癒し効果”を目的に開発を開始。04年には知能システムがライセンスを得て、05年から販売しており、今回、11月から大和ハウスが新たな販売先として加わる格好である。
大和ハウスのロボット事業は、08年にベンチャー企業のサイバーダインと総代理店契約を結び、歩行が困難な人でも杖なしで歩けるようにする装着型自立歩行支援ロボット「ロボットスーツHAL」のリース販売を開始したのがきっかけだ。今期40カ所以上の医療・介護施設に約100台のHALを納入しており、今回の2つの案件が加わることで、3種のロボットを取り扱うことになる。
なぜ、住宅メーカーである大和ハウスはロボット事業を行うのだろうか。
それは、将来の少子高齢化を睨んだ多角化戦略の一環だ。今後、ますます人口が減少するなかで新築住宅が先細りになるのは自明の理であるからだ。
厚生労働省によると、05年から25年にかけて、高齢者人口は約1070万人が増加すると予測。比率で言えば、65歳以上の高齢者人口は、現在の 5人に1人の割合から20年前後には約3人に1人にまで増えると予測されている(国立社会保障・人口問題研究所による)。これに対応し、高齢化を支える生活支援ロボットの市場も15年には3700億円、20年には1兆円に達するという試算がある(経済産業省による)。
こうした将来の労働力人口の減少や高齢化に対応し、大和ハウスは、2010年度を最終年度とする3年間の中期経営計画で、ロボット事業をリチウムイオン電池事業や海外(中国)事業などともに、新たな収益源となる次世代事業として強化しているのだ。
ロボット事業推進室の田中一正室長は「当初、2人でスタートした人員も東京と大阪を合わせて35人まで増え、今期で前年度比5倍以上の売上高2億 5000万円を目標としている」と説明する。
床下点検のモーグルは、高齢化が進む建築現場で作業員の負担を軽減するメリットが大きいため、自社グループ内での運用だけでなく、将来的には各地の工務店や建設会社向けの外販も期待できるという。
今回、販売するパロの場合では、日本国内では百貨店経由で販売されてきたこともあり、個人向けの“ペットロボット”という印象が強いが、海外では、米食品医薬品局(FDA)が09年に医療機器として承認しているほか、デンマークでは11年までに1000体の導入を計画し、パロを取り扱う公式な資格が設けられるなど、介護施設向けの介護機器として高く評価されている。
このため、大和ハウスでは、パロをHALとともに、これまで同社が施工してきた約2600カ所の医療・介護施設を中心に販売する考えだ。
ロボット事業は、少子高齢化を懸念するトヨタ自動車やホンダといった自動車メーカーも次世代事業として育成中である。住宅メーカー大手の大和ハウスがどれほど本気で望むのか。冒頭のコメントのように、建設関連業界の注目度も大きい。
(「週刊ダイヤモンド」編集部 山本猛嗣) 引用させていただきました。
どうですか?
絶対的に必要になると思いませんか?
こんにちは。
早速昨日の続きです。
男性にとって、「小便器の経ち位置」って 知らず知らずのうちに自身の本能が現れるものなんですね。
個室ではないオープンなスペースであるからこそなんでしょうが。
先ず、昨日の私の答えですが、私はど真ん中の『3』の位置を選択しました。
理由は、「先の人とひとつ置いて自分のスペースが取れていることと、次の人が1番を選べば、まだ自分との空間的なスペースが取れるから安心できるだろう。」との考えからです。
実際昨日の本に載っている統計データからは、2番目の人が選ぶ小便器は、『2』が一番多いのですが、その次には私同様 『3』の便器を選ぶようです。
ちなみに『2』を選ぶ理由も掲載されていましたが、
2番目の人は、1番目の人と離れた位置を選びたいのであるが、もっとも離れた『1』の便器は 手洗い器や入り口に近いことから、なんとなく落ち着かない感があるため、その隣の『2』の便器が選ばれる確立が高くなるのだそう。
その便器を選ぶ率を数値化すると、以下のようになるそうです。
5 4 3 2 1
88 40 56 60 24
これで見ると、やはり1番手前の『1』の便器は、よほど詰まっているとき以外使用頻度が低くなります。
無意識にとる行動だからこそ、この様な興味深い数値になるのですね。
早速昨日の続きです。
男性にとって、「小便器の経ち位置」って 知らず知らずのうちに自身の本能が現れるものなんですね。
個室ではないオープンなスペースであるからこそなんでしょうが。
先ず、昨日の私の答えですが、私はど真ん中の『3』の位置を選択しました。
理由は、「先の人とひとつ置いて自分のスペースが取れていることと、次の人が1番を選べば、まだ自分との空間的なスペースが取れるから安心できるだろう。」との考えからです。
実際昨日の本に載っている統計データからは、2番目の人が選ぶ小便器は、『2』が一番多いのですが、その次には私同様 『3』の便器を選ぶようです。
ちなみに『2』を選ぶ理由も掲載されていましたが、
2番目の人は、1番目の人と離れた位置を選びたいのであるが、もっとも離れた『1』の便器は 手洗い器や入り口に近いことから、なんとなく落ち着かない感があるため、その隣の『2』の便器が選ばれる確立が高くなるのだそう。
その便器を選ぶ率を数値化すると、以下のようになるそうです。
5 4 3 2 1
88 40 56 60 24
これで見ると、やはり1番手前の『1』の便器は、よほど詰まっているとき以外使用頻度が低くなります。
無意識にとる行動だからこそ、この様な興味深い数値になるのですね。
こんにちは。
今日も雲ひとつない快晴な空ですね。何処か遠出したくなるようなホントいい天気です。
出かけるコトで、思い出したこんな話を今日はしたいと思います。
毎日の生活の中で、多くの便器が並んでいるようなところで小用をたす事があまり無い私の場合、
公共の場や大オフィスのような空間で、数多くの便器が並んでいると いろいろな所に眼が行きながら情報入手するようにしています。
建築に関わる事も当然でしょうし、講習会等で休み時間に並ぶトイレ前の人の行動も見ていて飽きません。
例えば、こんな場合、男性の貴方だったら どの便器から使いますか?
(条件:現段階では、講習会等の休み時間で貴方がトイレ待ちの1番先頭になります。次から人が来ることも考慮してどの便器から選びますか?)
5 4 3 2 1 入り口
小便器 小便器 小便器 小便器 小便器 手洗い 扉
文章なのでイメージしながら選択していただくことになりますが、
これを先日目の当たりにしたとき、 思わず納得してしまいました。
実は、2年ほど前のブログにも書いたことのある「人間生活工学」 の本にもありましたが、
この場合、真っ先に5番の扉から1番奥のトイレから埋まります。
理由は、「他人に配慮しなくてよい・安心できる」場所だからです。
講習会会場のトイレで、先客が一人いた後が私だったので、この選択肢を思い出すことが出来たのでした。
では、2番目に入った 私は、 何処の場所の便器を選んだのでしょうか?
(2番目が貴方だったら、何処を選択されますか?) 直感で選択してみてください。
今日も雲ひとつない快晴な空ですね。何処か遠出したくなるようなホントいい天気です。
出かけるコトで、思い出したこんな話を今日はしたいと思います。
毎日の生活の中で、多くの便器が並んでいるようなところで小用をたす事があまり無い私の場合、
公共の場や大オフィスのような空間で、数多くの便器が並んでいると いろいろな所に眼が行きながら情報入手するようにしています。
建築に関わる事も当然でしょうし、講習会等で休み時間に並ぶトイレ前の人の行動も見ていて飽きません。
例えば、こんな場合、男性の貴方だったら どの便器から使いますか?
(条件:現段階では、講習会等の休み時間で貴方がトイレ待ちの1番先頭になります。次から人が来ることも考慮してどの便器から選びますか?)
5 4 3 2 1 入り口
小便器 小便器 小便器 小便器 小便器 手洗い 扉
文章なのでイメージしながら選択していただくことになりますが、
これを先日目の当たりにしたとき、 思わず納得してしまいました。
実は、2年ほど前のブログにも書いたことのある「人間生活工学」 の本にもありましたが、
この場合、真っ先に5番の扉から1番奥のトイレから埋まります。
理由は、「他人に配慮しなくてよい・安心できる」場所だからです。
講習会会場のトイレで、先客が一人いた後が私だったので、この選択肢を思い出すことが出来たのでした。
では、2番目に入った 私は、 何処の場所の便器を選んだのでしょうか?
(2番目が貴方だったら、何処を選択されますか?) 直感で選択してみてください。
こんにちは。
良くも悪くも、やはり講習会等で出張すると、つい「おのぼりさん」気分で 普段見たことが無いものなどを見ると、写真を撮ってしまいがちです。
先日の虎ノ門での講習会へ行く道すがら気になったのがこちら。
なんだか解りますか?
もう一枚の写真で・・・・・
電気自動車タクシー(EVタクシー)のバッテリー交換施設なのです。
詳しくは ↓ でご確認ください。
http://betterplace-jp.com/index.html
ニュースで以前貴方もごらんになった事があるんじゃないかと思いますが、実際この目で見ると、中まで覗き込んでしまうのが「おのぼりさん」なのでしょうか。
上のアドレスから飛んで映像や内容を読むほど、これからの時代の流れが少しわかったような気がする、にわか情報オヤジと化した私でした。。
こんにちは。
今日も台風一過のはずなのに、パーッと晴れないどんよりとした1日でした。
こんな時にはちょいとこんな1冊いかがでしょうか。
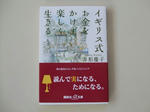
FM富士を聞いている私たち山梨県人には、大変なじみのある、井形慶子さんのエッセイ本です。
(毎週日曜日のAM9:30より30分の番組をされていらっしゃいます。)
実は私は、毎週ラジオで井形さんの話を聞いているが為か、なんとなく本を読むまでもなく『ひととなり』をイメージしてしまっていたので、あえて読まずに来ていました。
が、書店でこの本の表紙に惹かれ、買ってみたら井形さんの本だったと後で知りました。
読むほどに「無駄をしていない」つもりだったけど、とんでもなく消費好きだったな自分を鑑みることができましたし、『生活を楽しむ』事って何?という原点回帰にもなったかな~とも感じました。
ただ、生粋の日本人である自分がどこまで反芻できるかは疑問ですが、少なくとも生活スタイルの見本にはなる1冊だとも思います。
今日も台風一過のはずなのに、パーッと晴れないどんよりとした1日でした。
こんな時にはちょいとこんな1冊いかがでしょうか。
FM富士を聞いている私たち山梨県人には、大変なじみのある、井形慶子さんのエッセイ本です。
(毎週日曜日のAM9:30より30分の番組をされていらっしゃいます。)
実は私は、毎週ラジオで井形さんの話を聞いているが為か、なんとなく本を読むまでもなく『ひととなり』をイメージしてしまっていたので、あえて読まずに来ていました。
が、書店でこの本の表紙に惹かれ、買ってみたら井形さんの本だったと後で知りました。
読むほどに「無駄をしていない」つもりだったけど、とんでもなく消費好きだったな自分を鑑みることができましたし、『生活を楽しむ』事って何?という原点回帰にもなったかな~とも感じました。
ただ、生粋の日本人である自分がどこまで反芻できるかは疑問ですが、少なくとも生活スタイルの見本にはなる1冊だとも思います。

